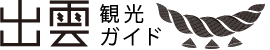秋の立久恵峡
絶景 立久恵峡
そそり立つ奇岩、柱石、老松古木が岩肌にからむ景色が約1km余りにわたって展開しています。岩の風化は激しく、ヒビ割れに雨水の浸食が加わり、多数の小さな谷が発達していて地形を複雑なものにしています。
その絶景は太古そのままの仙境とたたえられ、四季折々に変化する景観は訪れる人を楽しませてくれます。

立久恵山霊光寺
今から約1200年前の淳和天皇の時代、高野山の学僧浮雲律師がこの地方を行脚の折、河の深洲に毎夜光を放って呼ぶ声がありました。近くへ行くと、大きな青甲の亀が一体の如来を乗せ浮上してきました。律師はこの如来を天柱峯(てんちゅうほう)中腹の巌窟に定置されました。そして、天長4年亀渕山飛光寺が落慶し、大正8年に霊光寺として引きつぎ建立されました。
天柱峯の頂上付近に奥の院ががあります。この奥の院に人は住んでいませんが、夜中に木魚を叩く音が聞こえるといいます。それは昔からこの地に住む天狗の仕業と土地の人々はいうそうです。

五百羅漢(ごひゃくらかん)
霊光寺参道下からやや下ったがけの岩肌に石仏の群像があります。長い間、風雨にさらされ、半ば朽ち果てたものを含めると優に1000体を超えています。
古いものは木造で、石像は比較的新しく大正初期、霊光寺創建のとき、創建にたずさわった人々の手によって発願されました。